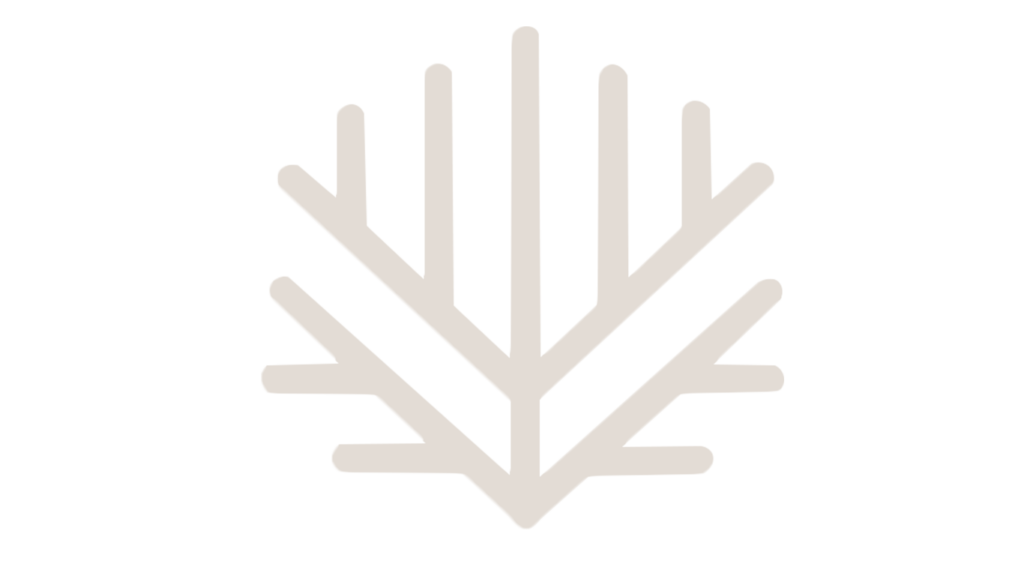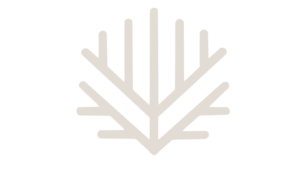誰かと向き合って話をするとき、「何を言うか」以上に「どう聴くか」が問われる場面があります。特に、部下との1on1や、取引先とのすり合わせ、あるいはトラブル時の謝罪や説明の席など、「難しい対話」ほど、言葉の裏にある相手の“感情”や“背景”を受け取る力が求められます。
ところが実際には、「何と返すか」「どう収めるか」と思考が先走り、肝心の“聴く”ことがおろそかになっているケースも少なくありません。そんなときに有効なのが、「今ここ」に意識を戻すマインドフルな聴き方です。
今回は、対話を単なる情報交換で終わらせないために、マネジメントの現場でできる小さな実践を取り上げます。
目次
Toggle1. 難しい対話のとき、心の中で起きていること
対話の場が難しく感じられるとき、私たちの頭の中では「どう切り返すか」「傷つけずに言えるか」と思考が忙しく働いています。その結果、相手の表情や間合いといった 非言語のメッセージ がすり抜けてしまいます。
実際、ある企業の人事責任者はこう話していました。「管理職研修で“沈黙が怖くて話しすぎてしまう”という声が多いんです。けれど、部下の本音はその 間 の中にあることが多いんですよね」。
つまり、難しい対話ほど、「間」や「戸惑い」に注意を向ける必要があります。
2. マインドフルに“聴く”とはどういうことか
マインドフルな聴き方とは、評価や判断をいったん脇に置き、相手の言葉がどこから出てきたのかに意識を向けることです。
たとえば、相手が途中で言葉に詰まったとき、つい「つまりこういうこと?」と助け船を出したくなります。でも、その一呼吸こらえて、「今、この人は何を感じているのかな」と心の内側で問いかけるだけで、空気が変わることがあります。
聴くとは、言葉の意味を理解するだけでなく、その背後にある「いまこの人にとって何が大事なのか」に触れようとする態度なのだと思います。
3. 「寄り添う」とは、同調ではなく関心を向けること
寄り添うことは、何でも「そうだね」とうなずくことではありません。むしろ、すぐに結論やアドバイスを出さず、「それがあなたにとってどういうことだったのか?」と丁寧に聴き返すことです。
ある中堅製造業の課長職の方が、「以前は“気持ちはわかるけどさ”が口癖でした。でもある時、それが部下の話を打ち切っていたことに気づいて、ぐっと飲み込む練習をしました」と話していました。
同調よりも、まだ語られていない部分 に関心を向けること。これが対話の信頼を築く土台になります。
4. 自分の内側とつながりながら聴く
相手の話に耳を傾けながら、自分の中にも湧いてくる感覚や違和感があります。たとえば、「なぜか急に肩に力が入る」「胸がざわつく」といった反応。これらは、言葉では表せない情報を自分の身体が教えてくれているサインです。
その感覚に気づきながら話を聴くことは、「反応せずに、そこにいる」という姿勢を整える助けになります。これは、自分を整えたうえで相手に向き合う、静かな準備のようなものです。
5. 実践ヒント:3秒だけ呼吸に意識を戻す
実際の対話の中で最も実践的な方法は、「あ、今つい反応しそうだな」と感じた瞬間に、3秒だけ呼吸に意識を戻すことです。
何かを深く吸い込み、静かに吐き出す。そのあいだ、自分の思考が再起動し、言葉の選び方にゆとりが生まれます。
これは瞑想ではなく、あくまで 隙間 をつくるための方法です。忙しい職場だからこそ、余白のあるやりとりが新しい空気を生むのです。
まとめ
難しい対話ほど、「何を言うか」ではなく、「どこから聴くか」が問われます。その“聴き方”は、決して技術の問題ではなく、日頃から自分の内側に耳を傾けているかどうかにかかっています。
判断を急がず、まず自分の身体感覚に注意を向ける。そして相手の沈黙や迷いに関心を持ちながら、ゆっくりと話を聴いていく。そうした積み重ねが、結果的に関係の質を底上げしていきます。
選択肢の一つとして、「反応」ではなく「選択」から言葉を発する対話を、現場で少しずつ試してみてはどうでしょうか。